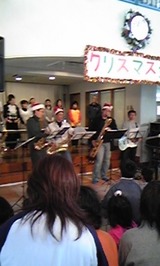スウェーデンでは、通訳及び訪問先のコーディネートをしてくださった方のご尽力により、素晴らしい研修とすることができました。
その方は、スウェーデン人とご結婚され、向こうに移住された日本人女性の方です。
スウェーデンで子育てもされているその方に、現地での生活について、いくつか質問させていただきました。
その内容を箇条書きで書きたいと思います。
(研修期間中、スウェーデンで通訳をしてくださった方は、コーディネートをしてくださったその方を含めて合計3名でした。そのうち2人が日本人妻の方。以下は、そのお二人からの聞き取り結果です。)
 《育児・出産》
《育児・出産》
・スウェーデンのほとんどの家庭が共働きで、子供が1歳になると保育所に預ける。
・スウェーデンでは、夫も育児休暇を30日以上取らなければならない。その場合は、80%の所得補償がある。(但し、補償金額に上限がある。)
・出産費用は、検診時からいっさい無料。地域の保健所のようなところで助産婦による定期検診を受け、出産のときのみ、施設の整った病院に行く。
(スウェーデンで出産された通訳さんのお一方は、「子供を産んだ日に、病院から「退院するか?」と聞かれて、それはさすがに無理だと伝え、もう一日入院させてもらった」というお話をされました。本当に出産する僅かの間しか病院にはいることができないとのこと。つまり、至れり尽くせりの日本の産婦人科とは、かなり違うようです。)
《教育》
・教育費は大学院まで無料。博士課程になると手当がもらえる。
・18歳になるまで児童手当が支給される。一人目が1,050クローネ、二人目が2,300クローネ、三人目が4,000クローネ。
(1クローネ・・約15円)
《医療》
・医療費は無料ではない。感覚として、むしろ高いと思う。
・1回の診療につき、200クローネかかる。(大学病院だと300クローネ。)
・風邪であろうが、心臓手術であろうが、病気の軽重に関わらず、一度の診療にかかる費用は200クローネである。
・一つの病気に対し、何回診療を受けても最高で1,200クローネまでで、その後それ以上費用がかかることはない。
・普通診療の場合、3ヶ月先まで待たねばならぬ事もしばしば。救急窓口であっても、血が出ていない限りは、4~5時間は待たされる。
・スウェーデンの病院は、基本的に公立。私立病院も僅かであるが存在し、そこではすぐに診療してもらえる。但し、1回につき500クローネほどかかる。
・18歳未満の子供の医療費は、救急病院での処置を除いては無料。
・歯の治療費は高い。1回の治療につき、500~600クローネ。
《消費税》
・消費税が25%ということで高税率ではあるが、表示金額に税金分が含まれているため、普段、買い物をする中で、税金が高いということを感じない。(分からない。)
《住居》
・住居費は高い。例えば、一戸建ての家を買うとしたら、3,000万円の購入資金に加え、更に家賃として毎月10万円ずつ(光熱費込み)支払っていくようなシステムになっている。スウェーデンにおいて、「家を買う」というのは、簡単なことではない。
《国民生活》
・物価は高い。(ex. 500mlペットボトルのジュースが、300~400円くらい。)
・国民の生活は、非常に質素である。
・貯金をする国民ではない。(貯金をするだけの余裕がないというのもある。)税金として、国に貯金している感覚。「国がお財布」のイメージ。
・外国人に対して、非常に寛容な国である。例えば、外国人がスウェーデンの学校に通えるチャンスは数多く設けてあり、また、人種差別をしたとなると厳しく罰せられる。なので、移住してくる外国人が多く、混血の子供も多くいる。スウェーデン国内でよく言われる冗談に、「あと100年もすれば、純粋なスウェーデン人はいなくなる」というのがある。
・出生率は高いが、これは移住してきた外国人が引き上げている。
・一部の銀行などで、「財政危機が起こる可能性がある」と言って、個人年金などの老後の商品を販売しているところもある。
いかがでしょうか?
スウェーデンでの生活が、少し垣間見えましたかね。
今日はここまでです。